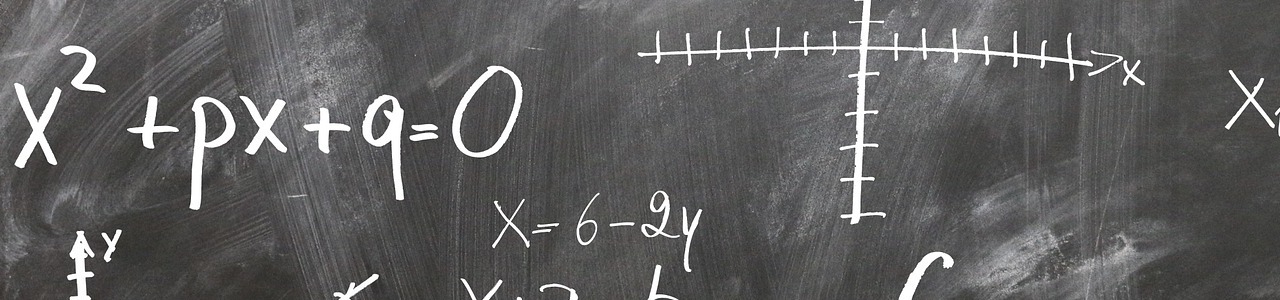沢畠 博之茨城県立日立第一高等学校 〒317-0063 茨城県日立市若葉町3-15-1 高校化学の溶液の学習において飽和水溶液の冷却による無水物の析出量を算出する場合は、析出量を直接与える比例式が教科書に記載されてい…
Read more... 水和水をもつ固体の析出量の比例式Ⅰ— 表を用いた導出—・中和と酸塩基滴定:pHを使う理由・酸塩基の定義・中和点・変曲点・当量点
山口 悟 茨城県立高萩清松高等学校 〒318-0001 茨城県高萩市赤浜1864番地 I 酸塩基の定義 酸と塩基の定義はたくさんあります。酸と塩基の定義について考えてみましょう。 II 中和点と変曲点 中和点と変曲点の講…
Read more... ・中和と酸塩基滴定:pHを使う理由・酸塩基の定義・中和点・変曲点・当量点非固形食を摂ることによる自律神経系への影響 & Come Come Happiness
student (2025), 4, 19-24 現在の日本では高齢化に伴う介護食市場が成長しており、2030年にはその規模は1,405億円に到達すると予測されている。介護食は高齢者や病気・障害などにより、通常の食事が…
Read more... 非固形食を摂ることによる自律神経系への影響 & Come Come Happinessフルクトースの甘味の温度依存性に関する研究
student (2025), 4, 14-18 フルクトースの甘味は大きな温度依存性を示す。本研究では、NMRスペクトル測定と分子軌道法計算から、フルクトースの分子構造に着目し、それが甘味に与える影響について評価した。…
Read more... フルクトースの甘味の温度依存性に関する研究納豆を用いた色素増感太陽電池の作製
student (2024), 4, 12-13 茨城県は、納豆の購入額ランキングの上位にランクインされている。しかし、実際には廃棄される量も少なくない。本研究では、納豆の食用以外での利用価値を見出すために、納豆の色素を…
Read more... 納豆を用いた色素増感太陽電池の作製時間発展を考慮した数理最適化モデルについての研究
student (2024), 4, 9-11 数理最適化とは,ある条件や制約の下で目的とする値の最大または最小値を求めることである.数理最適化を現実の問題に適応するとき,条件や制約の時間発展については,考慮されていない…
Read more... 時間発展を考慮した数理最適化モデルについての研究宇宙生活における生物餌料タマミジンコの青波長依存的な高効率増殖と季節性の解析
student (2024), 4, 1-8 現在,人間が月や火星などの衛生・惑星で生活するための有人活動基地の研究開発が進められている。近年,動物性タンパク質の必要性や食の多様性等の点で,宇宙生活においても動物性食糧の…
Read more... 宇宙生活における生物餌料タマミジンコの青波長依存的な高効率増殖と季節性の解析・分子間力:分子間力と分子間相互作用
山口 悟 茨城県立日立第一高等学校 〒317-0063 茨城県日立市若葉町3丁目15番1号 その1 分子間相互作用 分子間力とはいったい何なのでしょうか。高校化学の教科書や資料では,ちゃんと書いてあるのか無いのか,正直わ…
Read more... ・分子間力:分子間力と分子間相互作用融点降下に与える分子構造の影響
student (2023), 3, 43-47 融点降下とは、異なる成分が混入した不純物質における融点が、純物質と比較して低くなる現象である。本研究では、分子構造という新たな視点から融点降下を引き起こす要因について考察…
Read more... 融点降下に与える分子構造の影響静電気防止剤の静電気防止効果に関する研究
student (2023), 3, 39-42 毎冬、静電気の発生を防止するために色々な場面で静電気防止剤が使われている。静電気防止剤の主成分は界面活性剤であり、衣服に塗布することで表面に界面活性剤の膜が形成される。空…
Read more... 静電気防止剤の静電気防止効果に関する研究